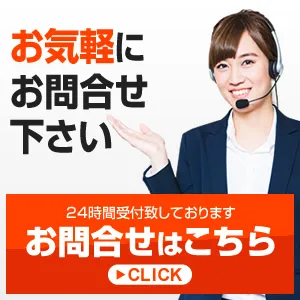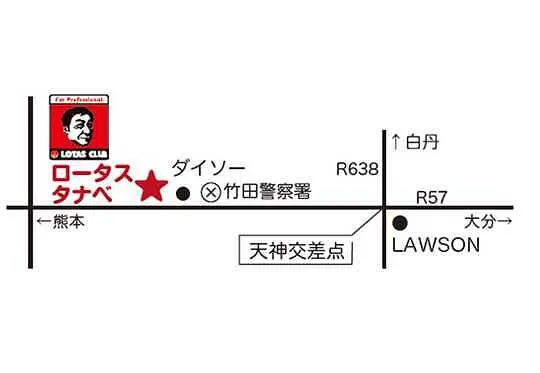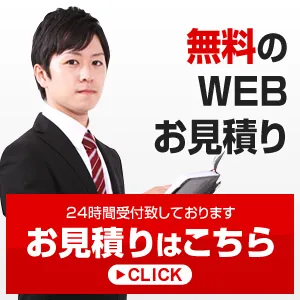- HOME
- 404エラー
404 Not Found
お探しのページは見つかりませんでした。
メニューからお探しのページを検索できます。
現在の在庫車情報
三菱 デリカD:52.4 C2 M パワーパッケージ 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36
支払総額84.7万円
本体66万円
諸費18.7万円
日産 セレナ2.0 ハイウェイスター S-H....
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36
支払総額84.7万円
本体66万円
諸費18.7万円
日産 セレナ2.0 ハイウェイスター S-H.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額78.6万円
本体66万円
諸費12.6万円
三菱 eKワゴン660 G
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額78.6万円
本体66万円
諸費12.6万円
三菱 eKワゴン660 G 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36
支払総額115.6万円
本体107.8万円
諸費7.8万円
スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ....
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36
支払総額115.6万円
本体107.8万円
諸費7.8万円
スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額143.5万円
本体138.3万円
諸費5.2万円
スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ....
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額143.5万円
本体138.3万円
諸費5.2万円
スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額65.3万円
本体59.4万円
諸費5.9万円
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額65.3万円
本体59.4万円
諸費5.9万円
 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36
支払総額84.7万円
本体66万円
諸費18.7万円
日産 セレナ2.0 ハイウェイスター S-H....
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36
支払総額84.7万円
本体66万円
諸費18.7万円
日産 セレナ2.0 ハイウェイスター S-H.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額78.6万円
本体66万円
諸費12.6万円
三菱 eKワゴン660 G
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額78.6万円
本体66万円
諸費12.6万円
三菱 eKワゴン660 G 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36
支払総額115.6万円
本体107.8万円
諸費7.8万円
スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ....
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:36
支払総額115.6万円
本体107.8万円
諸費7.8万円
スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額143.5万円
本体138.3万円
諸費5.2万円
スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ....
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額143.5万円
本体138.3万円
諸費5.2万円
スズキ キャリイ660 KCエアコン・パワステ.... 店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額65.3万円
本体59.4万円
諸費5.9万円
店長オススメ在庫有売却済み代行販売商談中新車販売未使用車他0件登録日 2025-07-14 20:35
支払総額65.3万円
本体59.4万円
諸費5.9万円
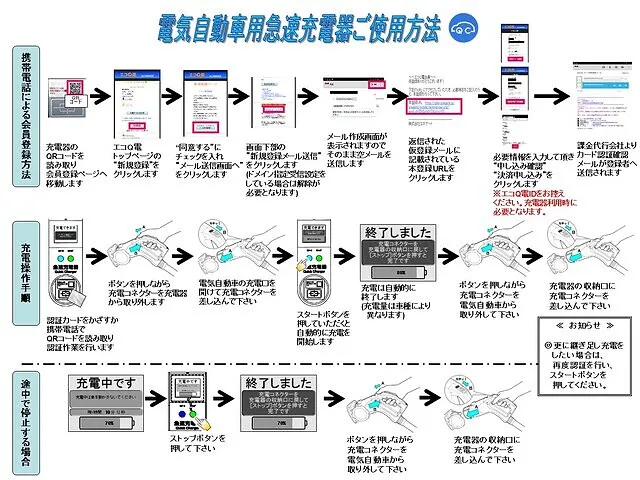 EV PHEV 電気自動車急速充電器
EV PHEV 電気自動車急速充電器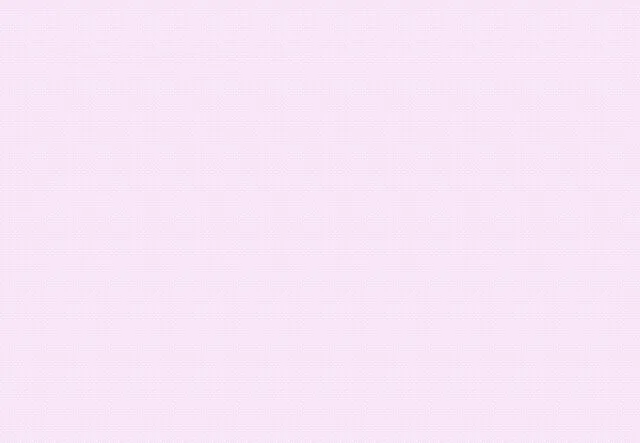 バックナンバーまとめ
バックナンバーまとめ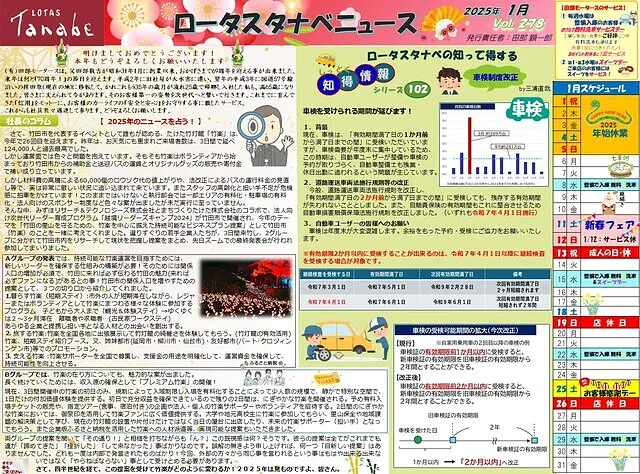 2025年バックナンバー
2025年バックナンバー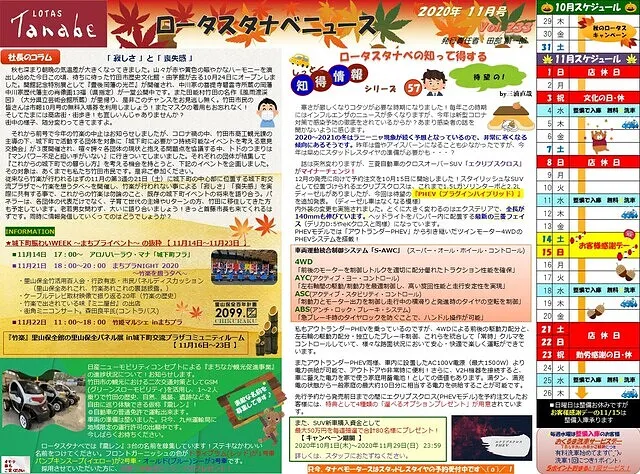 2020年バックナンバー
2020年バックナンバー 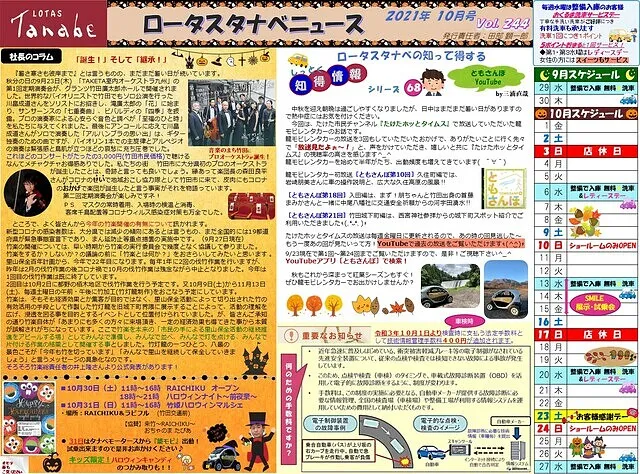 2021年バックナンバー
2021年バックナンバー 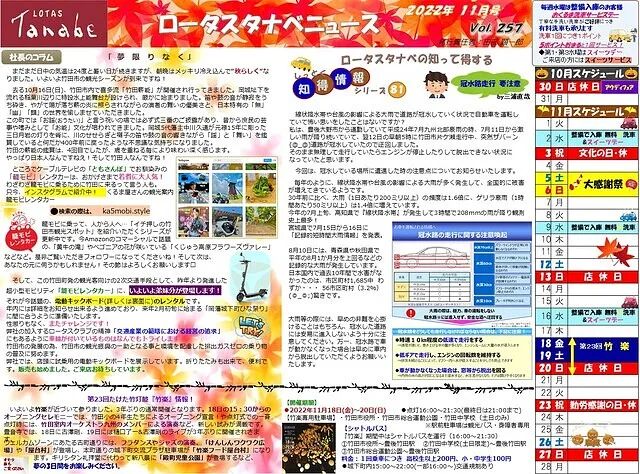 2022年バックナンバー
2022年バックナンバー  2023年バックナンバー
2023年バックナンバー  2024年バックナンバー
2024年バックナンバー  2015年バックナンバー
2015年バックナンバー 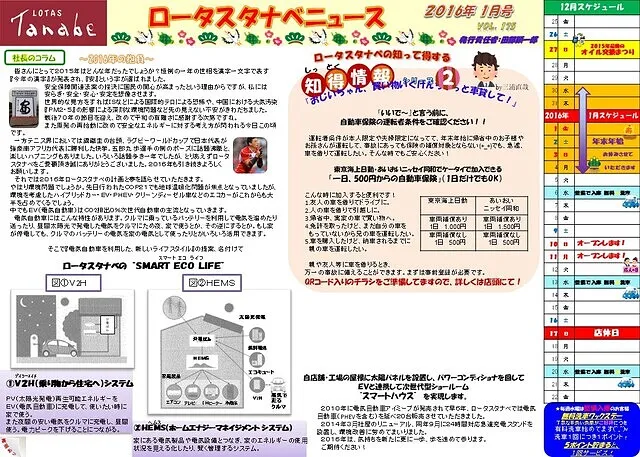 2016年バックナンバー
2016年バックナンバー  2017年バックナンバー
2017年バックナンバー 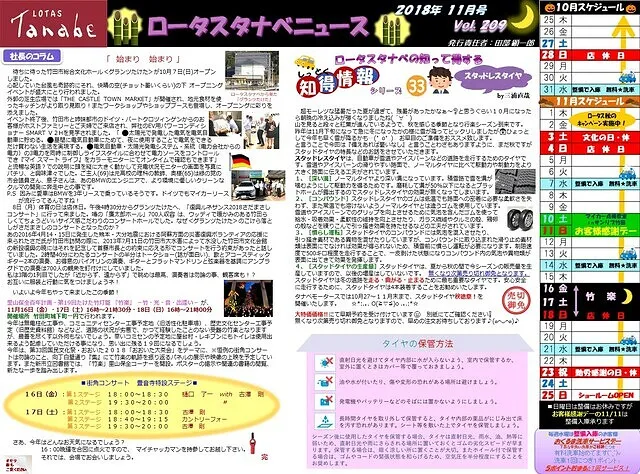 2018年バックナンバー
2018年バックナンバー 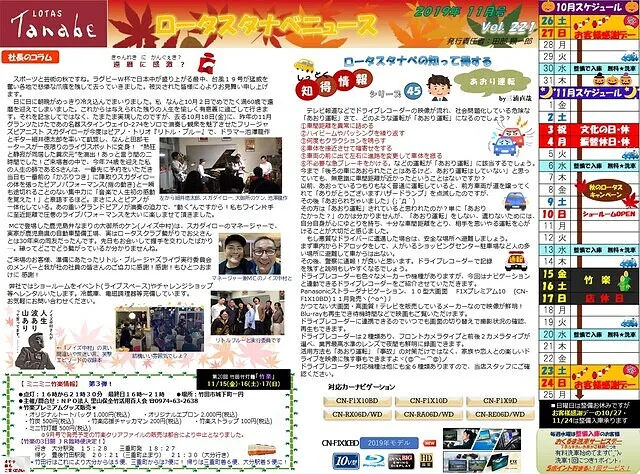 2019年バックナンバー
2019年バックナンバー  2010年バックナンバー
2010年バックナンバー 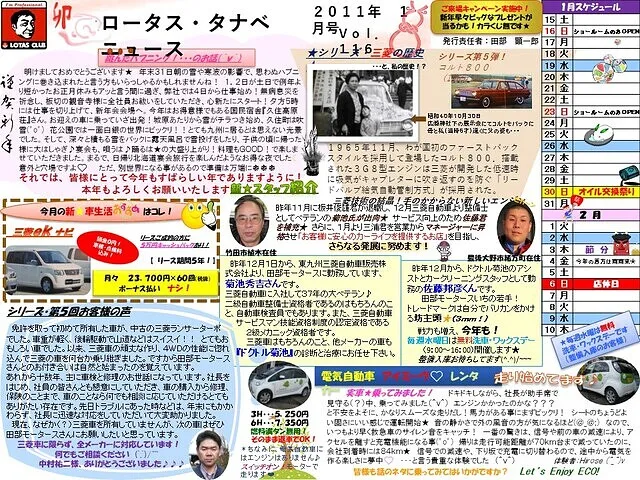 2011年バックナンバー
2011年バックナンバー  2012年バックナンバー
2012年バックナンバー  2013年バックナンバー
2013年バックナンバー  2014年バックナンバー
2014年バックナンバー